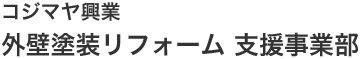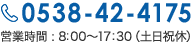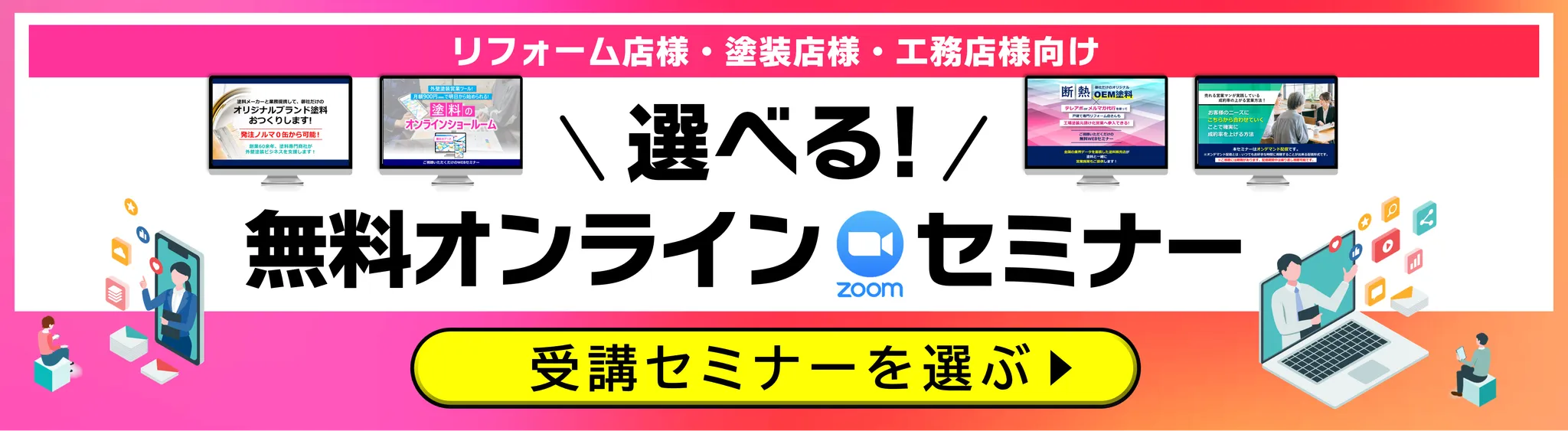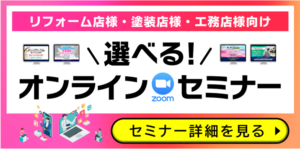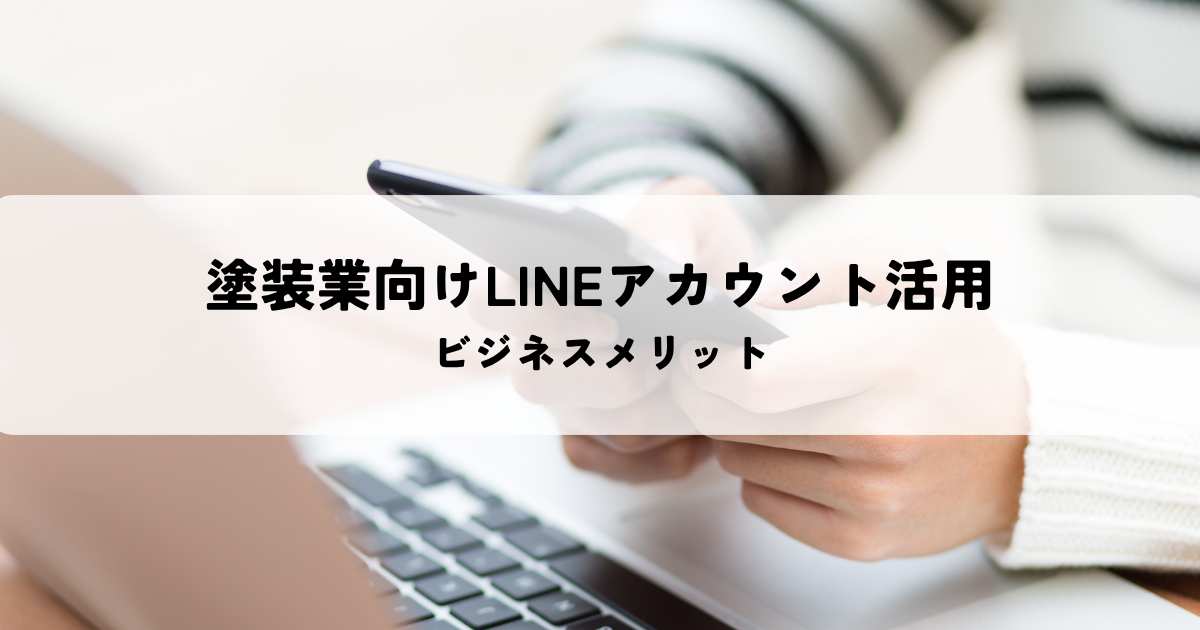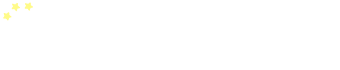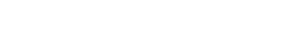一人親方の事業を拡大し、安定した経営基盤を築きたいと考えている方は多いでしょう。
個人事業主として活動してきた一人親方が法人化することで、税制面や社会保険、信用力といった点で様々な変化が生じます。
法人化にはメリットとデメリットが存在し、最適なタイミングを見極めることが重要です。
今回は、一人親方の方々が法人化について検討する際に役立つ情報を提供します。
法人化のメリット
税制面の優遇措置
個人事業主は所得に応じて税率が変動する累進課税が適用されますが、法人は一定の税率が適用されるため、高所得者ほど税負担軽減の効果が大きくなります。
特に、年間所得が800万円を超える場合、法人化による節税効果は顕著です。
法人税率は、中小企業の場合、800万円以下の所得に対しては15%、それ以上の所得に対しては23.2%です。
個人事業主の最高税率45%と比較すると、大幅な節税が期待できます。
ただし、法人化に伴う設立費用や維持費などを考慮する必要があります。
経費計上範囲の拡大
法人化すると、経費計上できる範囲が広がります。
個人事業主ではプライベートと事業の区別が曖昧になりがちな経費も、法人では事業活動に関連する費用として認められやすくなります。
例えば、自宅の一部を事務所として使用する場合、その分の家賃や光熱費を計上できます。
また、事業主の給与や賞与も経費として計上でき、節税に繋がります。
さらに、生命保険料や退職金なども経費計上できるケースがあります。
経費計上の範囲を広げることで、税金を削減し、利益を増加させることができます。
社会保険への加入
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人化すると健康保険と厚生年金に加入できます。
社会保険は、国民健康保険や国民年金よりも手厚い保障を受けられる点がメリットです。
また、従業員を雇用する際には、社会保険加入は必須となります。
社会保険への加入は、事業主自身の生活の安定だけでなく、従業員の確保や定着にも繋がるため、事業拡大を目指す上でも重要な要素です。
信用力向上と事業拡大
法人化は、取引先や金融機関からの信用度を高めます。
法人は個人事業主と比べて、より安定した経営基盤を持つと見なされるため、大規模な取引や融資の申し込みが容易になります。
信用力の向上は、事業の拡大や新たなビジネスチャンスの獲得に繋がります。
また、大手企業との取引においても、法人格は有利に働きます。
信用力の向上は、事業の継続性と成長に大きく貢献します。
リスク軽減と事業承継
法人化により、事業リスクと個人資産を分離できます。
個人事業主の場合、事業の失敗によって個人資産が差し押さえられるリスクがありますが、法人は会社と個人が別個の主体として扱われるため、リスクを軽減できます。
また、事業承継においても、法人化はスムーズな継承を可能にします。
株式譲渡や相続によって、比較的容易に事業を引き継ぐことができます。
法人化のデメリット
設立費用と手続きの手間
法人化には、会社設立費用や手続きに時間と費用がかかります。
設立費用には、定款作成費用、公証役場での認証費用、登記費用、印鑑作成費用などが含まれます。
手続きも複雑で、専門家のサポートが必要となる場合もあります。
これらの費用と手間は、事業開始前の準備段階で十分に考慮しておく必要があります。
事務作業と会計処理の負担増加
法人化すると、個人事業主よりも複雑な会計処理や税務申告が必要になります。
毎月の記帳、決算処理、税務申告など、事務作業の負担が増加します。
これらの業務を自身で行うには専門知識が必要であり、時間的な制約も大きいため、税理士などの専門家に依頼するケースが多いです。
赤字の場合の税金負担
個人事業主の場合、赤字であれば所得税はかかりませんが、法人は赤字であっても法人住民税を支払う必要があります。
法人住民税は均等割(自治体によって金額が異なるが、年間7万円程度が一般的)と法人税割で構成されます。
法人税割は通常、法人税額に応じて計算されますが、赤字の場合でも一定の金額を支払う必要があります。
資金の自由度低下
法人化後は、会社の資金を自由に使うことができなくなります。
事業主個人の生活費は、役員報酬として会社から支払われることになります。
役員報酬は、会社の業績に左右されるため、自由に使える金額に制限が生じます。
法人化の最適なタイミング
年間売上1000万円超え
年間売上高が1000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
しかし、法人化をすることで、消費税の課税基準がリセットされ、2年間は消費税の納付義務が免除されます。
このタイミングでの法人化は節税に繋がる可能性があります。
課税所得900万円超え
課税所得が900万円を超えると、所得税率が法人税率よりも高くなるため、法人化による節税効果が大きくなります。
所得税率は累進課税であるのに対し、法人税率は一定であるため、高所得者ほど法人化によるメリットが大きくなります。
社会保険加入の検討
国民健康保険や国民年金よりも手厚い保障を受けたい、または従業員を雇用する予定がある場合、社会保険への加入を検討するタイミングが法人化の検討時期となります。
社会保険への加入は、事業主自身の生活の安定だけでなく、従業員の確保や定着にも繋がります。
事業拡大と従業員雇用
事業拡大を計画し、従業員を雇用する予定がある場合、法人化は有効な手段です。
法人化により信用力が向上し、資金調達や取引先開拓が容易になります。
また、従業員にとって魅力的な雇用条件を提供できるようになり、優秀な人材の確保に繋がります。

法人化の手続きと会社形態
株式会社と合同会社の比較
法人化には、株式会社と合同会社の2つの主要な会社形態があります。
株式会社は、社会的信用度が高く、大規模な事業展開に適していますが、設立費用や運営コストが高くなります。
合同会社は、設立費用が安く、運営が簡素なため、小規模な事業に適しています。
事業規模や将来的な展望を考慮して、最適な会社形態を選択する必要があります。
設立手続きの流れ
法人化の手続きは、定款の作成・認証、資本金の払い込み、登記申請など、複数のステップからなります。
これらの手続きは複雑で、専門家のサポートが必要となる場合もあります。
手続きの流れを事前に把握し、必要な書類や手続き期限などを確認しておくことが重要です。
会社設立代行サービスの活用
会社設立代行サービスを利用することで、設立手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。
専門家が書類作成から申請までを代行するため、事業主は本業に専念できます。
ただし、代行費用が発生することを考慮する必要があります。
FAQよくある質問
Q1:法人化後、すぐに税金のメリットを実感できますか?
A1:法人化による税制上のメリットは、法人設立後すぐに現れるわけではありません。
設立費用や経費の変動など、様々な要素を考慮する必要があります。
税制上のメリットを最大限に享受するには、適切な経理処理や税務対策が不可欠です。
Q2:法人化は、建設業許可に影響しますか?
A2:建設業許可は、個人事業主から法人へそのまま引き継ぐことはできません。
法人化を検討する際には、新たに法人として建設業許可を取得する必要があります。
手続きに時間を要するため、余裕を持って準備を進めることが重要です。
Q3:法人化に最適な時期は、どのように判断すれば良いですか?
A3:法人化の最適な時期は、事業規模、収益、将来計画など、様々な要因によって異なります。
税理士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な時期を判断することが重要です。
まとめ
一人親方の法人化は、税制上の優遇措置による節税効果、社会保険への加入、信用力向上による事業拡大、リスク軽減など多くのメリットがあります。
一方で、設立費用や手続きの手間、事務作業の増加、赤字時の税金負担、資金の自由度低下などのデメリットも存在します。
法人化を検討する際は、これらのメリットとデメリットを比較検討し、年間売上高、課税所得、社会保険加入の必要性、事業拡大計画などを考慮して、最適なタイミングを見極めることが重要です。
また、手続きの複雑さから、会社設立代行サービスの活用も検討すると良いでしょう。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
創業60余年塗料専門商社コジマヤグループ
コジマヤ興業(株)リフォーム支援事業部
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡